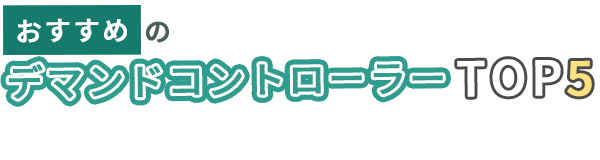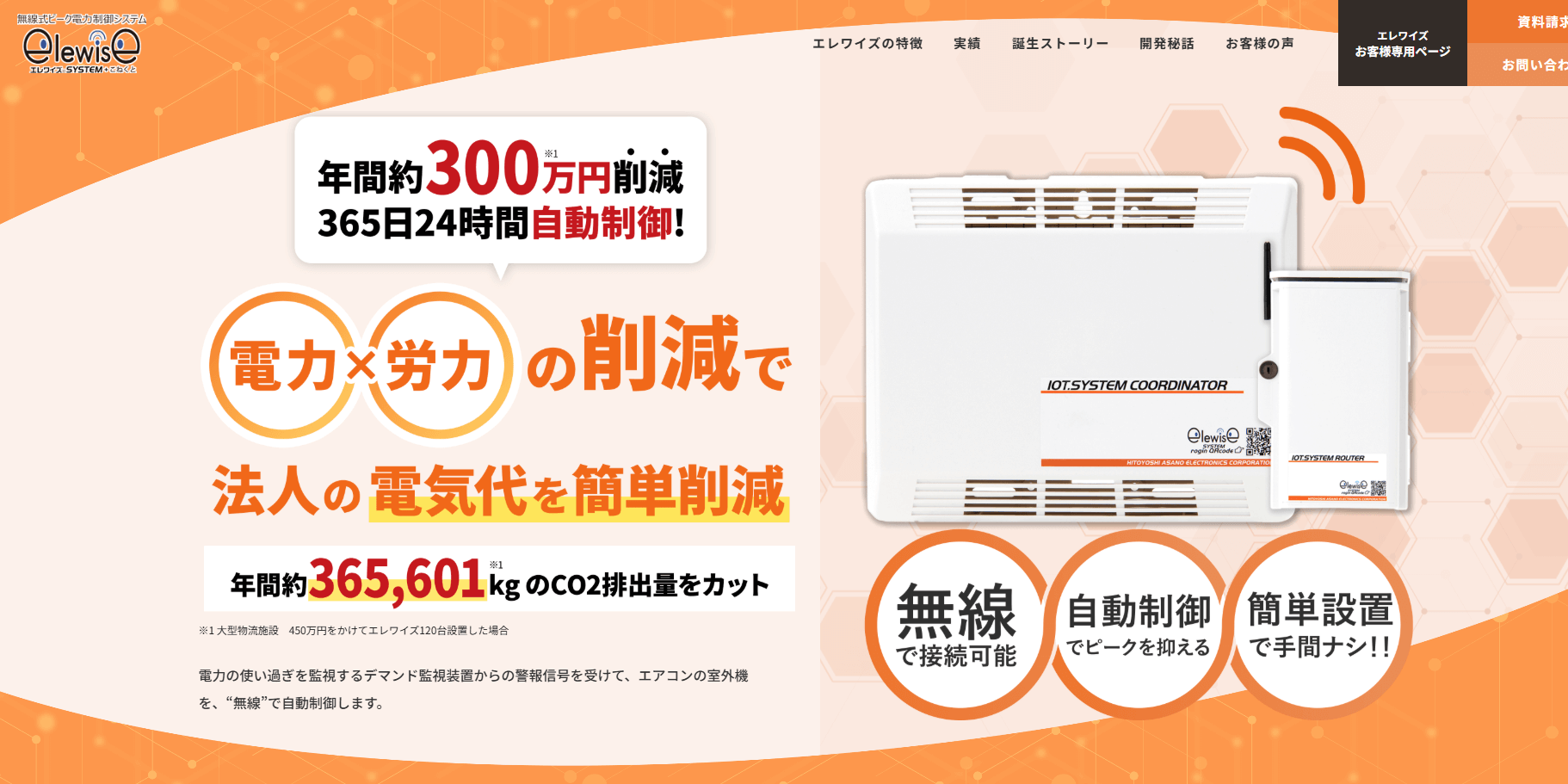電気代の高騰が続く中、企業や施設の経営を圧迫する電力コストの削減は急務となっています。その解決策として注目を集めているのがデマンドコントロールです。最大需要電力を適切に管理することで、基本料金を大幅に削減できるこのシステムは、初期投資を短期間で回収できる効果的な省エネ手法として導入が進んでいます。
デマンドコントロールとは
デマンドコントロールとは、30分間の平均使用電力量である「デマンド値」を監視し、設定した目標値を超えないよう電力使用を制御するシステムです。電力会社との契約では、過去1年間の最大デマンド値が基本料金の算定基準となります。この最大デマンド値を抑制することで、年間を通じて基本料金を削減できる仕組みとなっています。デマンドコントロールの仕組み
具体的には、デマンド監視装置が常時電力使用量を計測し、30分間の予測値が目標を超えそうになると警報を発します。さらに自動制御機能を備えたシステムでは、空調機器の出力調整や一時停止などを自動で実行し、ピークカットを実現します。基本料金削減の効果
一般的な高圧受電施設の場合、基本料金は最大デマンド値1kWあたり月額1,500円から2,000円程度で設定されており、仮に100kWの削減に成功すれば月額15万円から20万円、年間では180万円から240万円もの基本料金削減が可能となります。デマンドコントロールの種類
デマンドコントロールシステムは大きく分けて3つのタイプが存在します。まず監視型は、現在のデマンド値をリアルタイムで表示し、目標値超過の恐れがある場合に警報で知らせるシステムです。次に手動制御型は、警報を受けて担当者が手動で機器を停止させる方式となっています。最後の自動制御型は、あらかじめ設定した優先順位に従って自動的に機器を制御し、人的負担を最小限に抑えながら確実なデマンド抑制を実現します。
導入施設の規模や運用体制に応じて最適なタイプを選択することが重要であり、とくに24時間稼働の施設や人手不足に悩む事業所では自動制御型の導入効果が高くなっています。
デマンドコントロールを導入するメリット
デマンドコントロール導入の最大のメリットは、電気料金の大幅な削減です。基本料金は契約電力に比例するため、最大デマンド値を10%削減できれば基本料金も10%削減されます。500kWの契約電力をもつ施設が50kW削減に成功した場合、年間120万円から150万円の経費削減が実現可能となります。この削減効果は導入初年度から継続的に得られるため、設備投資の回収期間は通常2年から3年程度と短期間で済みます。
エネルギー使用の見える化による効率化
エネルギー使用の見える化により、無駄な電力消費を発見しやすくなることも大きな利点です。時間帯別、設備別の電力使用状況が詳細に把握できるため、効率的な省エネ対策の立案が可能となります。環境負荷低減と企業価値向上
電力使用量の削減はCO2排出量の削減に直結し、企業の環境負荷低減に貢献します。SDGsへの取り組みが重視される現代において、環境配慮型経営の実践は企業価値向上にもつながります。安定した事業運営の支援
電力需給がひっ迫する夏季や冬季において、計画的な電力使用が可能となることで、安定した事業運営を維持できます。複数拠点の一元管理とデータ活用
デマンドコントロールシステムの多くはクラウド型サービスとして提供されており、複数拠点の一元管理も容易です。本社から各支店や工場の電力使用状況をリアルタイムで監視し、全社的なエネルギー管理体制を構築できます。データの蓄積により、季節変動や曜日別の傾向分析も可能となり、より精度の高い省エネ計画の策定に役立ちます。
補助金制度の活用による導入コスト軽減
補助金制度の活用により、導入コストをさらに抑えることも可能であり、自治体や国の省エネ補助金を利用すれば、初期投資の30%から50%程度の補助を受けられるケースもあります。デマンドコントロールを行う際の注意点
デマンドコントロールは電力コスト削減や省エネに有効な手段ですが、導入にあたっては施設や業務への影響を慎重に考慮する必要があります。適切な運用と管理を行うことで、効果を最大化しつつ安全・快適な環境を維持できます。業務への影響を考慮した運用
デマンドコントロール導入にあたっては、過度な電力抑制による業務への影響を慎重に検討する必要があります。製造業では生産ラインの停止が品質や納期に影響し、医療施設では患者の安全性に関わる機器の制御は避けなければなりません。オフィスビルにおいても、空調の過度な抑制は従業員の作業効率低下や健康被害につながる恐れがあるため、快適性と省エネのバランスを考慮した運用が求められます。
施設特性に応じたシステム選定
システム選定時には、施設の特性に応じた機能の確認が不可欠です。24時間稼働の施設では自動制御機能が必須となりますが、日中のみ稼働する事務所では監視型でも十分な効果が得られることもあります。運用体制と教育の重要性
運用面では、担当者の教育とマニュアル整備が成功の鍵となります。警報発生時の対応手順を明確化し、誰もが適切に対処できる体制を構築しなければなりません。目標値の見直しと契約電力の管理
定期的な目標値の見直しも重要であり、季節変動や事業拡大に応じて適切な設定値を維持する必要があります。契約電力の変更には電力会社との協議が必要となり、一度下げた契約電力を再度上げる際には時間と手続きが必要となるため、将来の事業計画を考慮した慎重な判断が求められます。メンテナンスとデータ管理
メンテナンス体制の確立も欠かせません。センサーの精度維持や通信機器の動作確認など、定期的な保守点検により、システムの信頼性を確保する必要があります。データのバックアップ体制も整備し、トラブル発生時の迅速な復旧を可能にしておくことが、安定した省エネ効果の継続につながります。