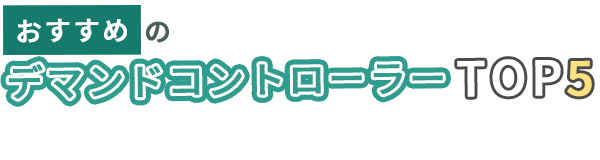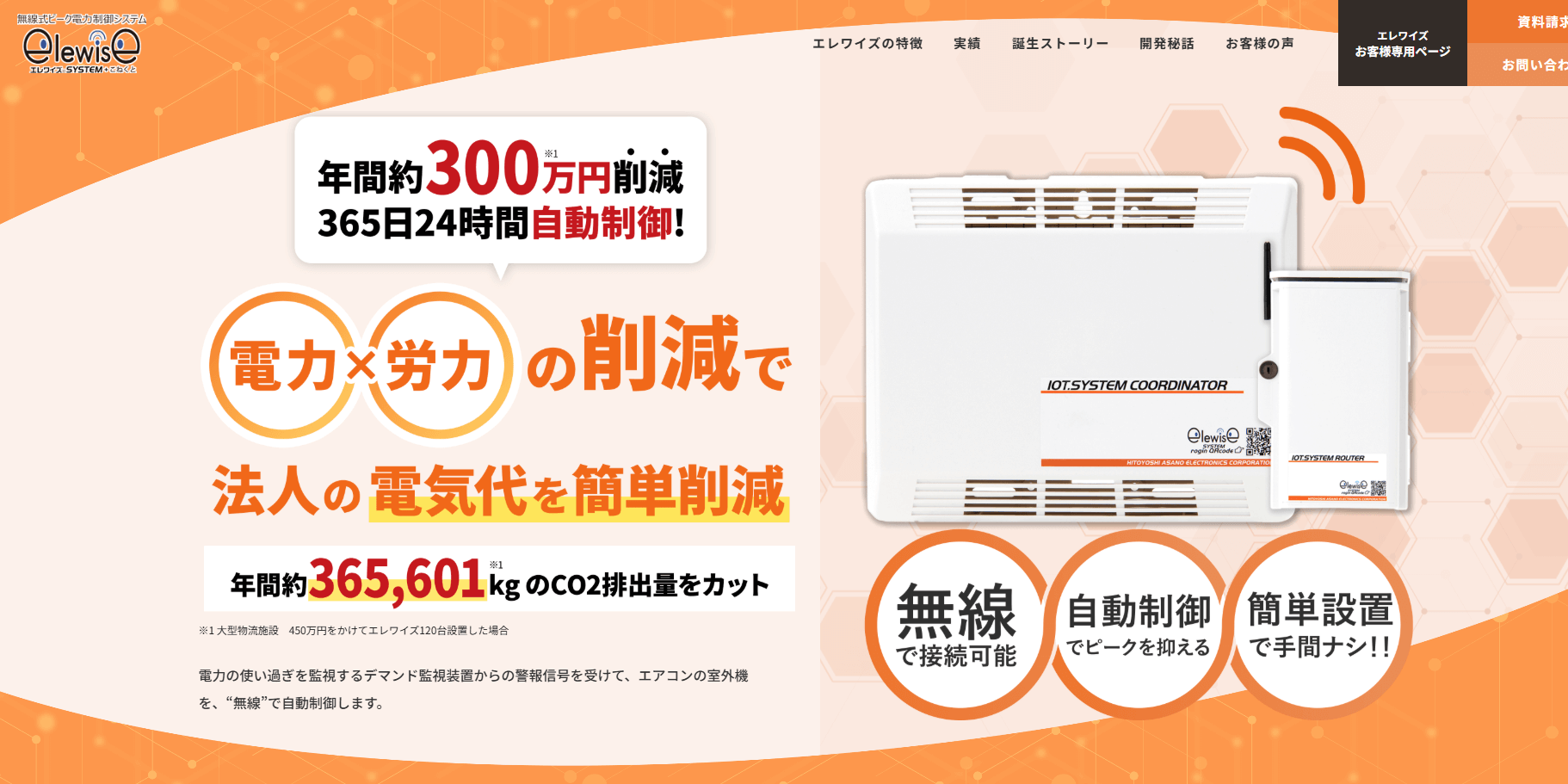電気料金の削減は企業経営において重要な課題となっています。とくに契約電力の基準となるデマンド値は、基本料金に直接影響を与える重要な指標です。しかし、このデマンド値の仕組みや管理方法について正確に理解している企業は意外と少ないのが現状でしょう。本記事では、デマンド値と電気料金について詳しく解説します。
デマンド値と電気料金の関係
デマンド値とは、30分間の平均使用電力を指し、高圧受電契約を結んでいる企業にとって基本料金を決定する重要な要素となっています。契約電力と基本料金の関係
電力会社は過去12か月間の最大デマンド値を基準に契約電力を設定し、これが基本料金の算出根拠となるのです。たとえば、最大デマンド値が500kWの企業の場合、基本料金単価が1,716円であれば月額85万8,000円の基本料金が発生することになります。デマンド値の影響とコスト増
さらに重要なのは、一度でも高いデマンド値を記録してしまうと、その後12か月間は高い基本料金を支払い続けなければならないという点でしょう。仮に通常300kWで推移していた企業が、夏の猛暑日に一時的に500kWを記録した場合、年間で約412万円もの追加コストが発生する計算になります。このようにデマンド値は企業の電気料金に大きな影響を与えるため、適切な管理が不可欠です。
デマンド値の計測方法
デマンド値は15分ごとに計測され、30分単位で平均値が算出されるという仕組みになっており、瞬間的な電力使用量の増加にも注意が必要となります。業種ごとのデマンド値の特性
とくに製造業では、複数の設備を同時に稼働させた際にデマンド値が急上昇するケースが多く見られるでしょう。オフィスビルでは、夏季の空調負荷が最大の要因となることが一般的で、午後2時から3時にかけてピークを迎える傾向があります。このような特性を理解し、業種や施設の特徴に応じた対策を講じることが、電気料金削減の第一歩となるのです。
デマンド値を抑える方法
デマンド値を効果的に抑制するためには、まず自社の電力使用パターンを正確に把握することから始める必要があります。30分デマンド計や電力監視システムを活用して、時間帯別、設備別の電力使用状況をデータ化し、ピーク時間帯と主要な電力消費設備を特定することが重要です。運用面での改善
具体的な削減方法として、まず運用面での改善が挙げられるでしょう。空調設定温度の適正化により、夏季は28度、冬季は20度に設定することで、約10%の電力削減が可能となります。また、生産設備の稼働時間をずらすピークシフトも効果的で、たとえば昼休み時間帯に一部の設備を停止させることで、最大デマンド値を20%程度削減できた事例も報告されています。
設備面での対策
設備面では、LED照明への切り替えによって照明電力を約60%削減できるほか、高効率空調機への更新で30%程度の省エネが実現可能です。さらに、デマンド監視装置を導入することで設定値を超えそうな場合にアラートを発信し、事前に対策を講じることができるようになります。ある製造業の事例では、デマンド監視と運用改善を組み合わせることで年間約240万円の基本料金削減を達成しました。
継続的な取り組みの重要性
重要なのは、これらの対策を単独で実施するのではなく、複合的に組み合わせることです。従業員への省エネ意識の啓発も欠かせない要素であり、定期的な研修や見える化ツールの活用によって、全社的な取り組みとして推進することが成功の鍵となるでしょう。継続的なPDCAサイクルを回しながら段階的に改善を進めていくことが、確実な成果につながります。
デマンドコントロールの種類と導入手順
デマンドコントロールシステムには大きく分けて手動制御型と自動制御型の2種類があり、企業の規模や予算に応じて選択することが可能です。手動制御型は、デマンド監視装置からの警報を受けて担当者が手動で機器を停止させる方式で、初期投資が10万円から30万円程度と比較的安価に導入できます。一方、自動制御型は設定値を超えそうになると自動的に空調や照明を制御する高度なシステムで、50万円から200万円程度の投資が必要となりますが、人的ミスを防ぎ確実な制御が可能となるメリットがあります。